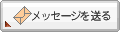2013年09月10日
長野・「蘭亭山荘 Art museum・Ⅰ(士の志)」
現在 山間地の過疎化が 急速に 進んでいる。
私の 長野の山荘周辺(南木曽町吾妻蘭)も 朽ちるように廃屋になった家などがみられる。
かわいそうに 家が泣いている。・・・ ・・
”町並み保存整備が 地域周辺・生活に 大きな影響を与えつつある”
町並み家屋保全等が 国土の力 現代に生きる我々の人間力・・・にも繋がっている。
私は長男であるため毎年 長野に帰省し先祖のお墓(3基)に住職にお経等をあげていただいている。
私の生家は既に無い。 生家は街道に面して広場を持っていたため、木曽谷と伊那谷を結ぶバス路線の中継の休み所の一つになっていた。 バスの旅人たちが、庭の大きな桜の木を眺めながら我が家で一服・逗留していた。祖父が趣味人であったためか 旅人である文人達が逗留するなどで 書かれた書・絵などが残されている。私が小学校3年生の頃 家を移転しなくてはいけなくなり、多くの家財・署・絵画などを随分と処分したようであるが。
・・
現在 100年ぐらい経つ育った家を若干改修し サマーハウスに利用している。
”””歴史 とは 過去を現代に繋ぎ生かす こと!!!”””
ここで 長野・「蘭亭山荘」の Art museumⅠ(士の志) を紹介しよう。
{改修の時 壊れていた赤黒い艶を持った船箪笥を処分してしまったのを悔やんでいる。}
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
***。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。***
①山荘駐車場と別庭(北原教授剪定の 紅葉、松、さつき、山躑躅、楓、銀杏、紫陽花等)
{別庭の奥でジャガイモを2回ほど収穫したが、今はブルーベリーの苗木を植えている。
1か月の滞在では残念だが思うように育っていない。}

***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
②山荘玄関上(山荘に在住の場合に掲示) 北原教授篆刻作品「蘭亭山荘」海山著
幸喜洋人先生指導
蘭亭は中国浙江省紹興市の蘭渚山麓にあり、東晋の書家王羲之(おうぎし)が文人を集めて宴を開く。

***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
③山荘 3者のコラボ作品 と 母の箪笥 母好みの琉球畳
北原教授篆書と寿紗代先生ガラスプレートと小椋弘氏の高野槇木製額
” 岳 を 表現している ””

***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
④山荘 和室の掛け軸 所縁のある「蘭の墨絵」
蘭(科)は、単子葉植物の科のひとつで、その多くが美しく、独特の形の花を咲かす。世界に15000種、日本に230種がある。鑑賞価値が高いものが多く、栽培や品種改良が進められる。

***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑤山荘 仏間の上の横額 「剣道士磨墨」
リーダー(士)の あるべき姿が書かれている。
「磨墨」は 中国の墨子によっている。 地域社会のため、人としての道・勉学を研鑽することを意味している。
⇒https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%A8%E5%AD%90
「剣道士」は 人のため世の中を改善しようとする 政治家等の"胆識”あるリーダーの 行動・覚悟を意味している。

***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑦山荘 琉球をイメージする墨絵横額 「芭蕉と雀・野菊」
初めて 祖父の部屋で この墨絵の巻紙を観たときは、架空題材をとらえたものと思った。しかし 沖縄に移住し 沖縄の城をめぐる中で「芭蕉」「雀」・「野菊」は まさに沖縄の地のものだとの気づき驚いた。 沖縄・長野の赤い糸のような結びつき・・・ ・・ ・ 大切にしたい。

***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑧山荘 母好みの 日本間 襖(表・裏)
母は 今年で90歳を迎える 理髪師をしていたが デザイナーになりたかったそうである。
名古屋生まれであったが 年少のころ 叔父の所に引き取られて大切に育てられたようだ。
小学校に行くときは、何時も 丸に引き両の紋(新田源氏の紋?)のある着物を着て馬に乗せられ
通ったと少しいやな顔をみせて語ったことを覚えている。
・・
そういえば、私の少年期 刺繍の襟のある仕立てられたシャツ等を母から よく着せられた。
料理も ケチャップライス など あの当時の 山村ではモダンな人であった。
{{襖は手品師 たった1センチメートルで異次元の空間を創る。}}
山荘の日本間は8畳が2つある。”襖の表・裏”で2つの違った雰囲気の日本間が出現。
襖を取り去れば 16畳の広間となる。
襖のデザイン紙は 40年ほど前に 母が選んだものである。母の美的センスが伺える。
表:
裏:
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑨山荘 祖母に伝えられた銅鏡
銅鏡には「厄除けの南天の木、梅の木、笹」などが描かれている。
「上藤原久共」との刻印がある。

***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑩山荘 日本刀・脇差(警察署に届け済)・バックは蘭亭深山の書・屏風
{陶芸家:上江洲茂生先生作陶「片口泡盛大杯」}
{義弟たちが許可を得て狩猟した日本カモシカ角の刀掛け}

私が34歳の時 10年以上 胃癌で闘病していた父が亡くなった。 日本間の 父の遺体の胸の上には 祖父が日本刀を横に置いていた。 日本刀をみると鞘から少し出されて抜き身がキラリと光って見えた。 その時に 魔物等を避けるための先祖から続く作法であると祖父から諭された。 このことは今でもはっきりと脳裏に残っている。 また、父が亡くなって10年後、遺骨を分骨し京都の本山へ 母たちと納骨しに訪れた ・・・ ・・ ・ 人生 普段の生活からは窺い知れない決まり事が多くあるものだ。
・・父の死を通して 守り刀として日本刀を保持している意味等を知った・・・ ・・ ・
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
家には歴史・人の温もり等がある。 人の生き様、伝統の品々、周りの自然等も含め全てArts である。
大切にしなくてはいけない事 ” 伝える ”・・・ ・・ ・ !!!
{{蘭亭山荘 Art museum は → 蘭亭山荘 Art museumⅡ(能・小面のこころ) へ続く}
☛ https://kitahara.ti-da.net/e5312078.html
私の 長野の山荘周辺(南木曽町吾妻蘭)も 朽ちるように廃屋になった家などがみられる。
かわいそうに 家が泣いている。・・・ ・・
”町並み保存整備が 地域周辺・生活に 大きな影響を与えつつある”
町並み家屋保全等が 国土の力 現代に生きる我々の人間力・・・にも繋がっている。
私は長男であるため毎年 長野に帰省し先祖のお墓(3基)に住職にお経等をあげていただいている。
私の生家は既に無い。 生家は街道に面して広場を持っていたため、木曽谷と伊那谷を結ぶバス路線の中継の休み所の一つになっていた。 バスの旅人たちが、庭の大きな桜の木を眺めながら我が家で一服・逗留していた。祖父が趣味人であったためか 旅人である文人達が逗留するなどで 書かれた書・絵などが残されている。私が小学校3年生の頃 家を移転しなくてはいけなくなり、多くの家財・署・絵画などを随分と処分したようであるが。
・・
現在 100年ぐらい経つ育った家を若干改修し サマーハウスに利用している。
”””歴史 とは 過去を現代に繋ぎ生かす こと!!!”””
ここで 長野・「蘭亭山荘」の Art museumⅠ(士の志) を紹介しよう。
{改修の時 壊れていた赤黒い艶を持った船箪笥を処分してしまったのを悔やんでいる。}
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
***。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。***
①山荘駐車場と別庭(北原教授剪定の 紅葉、松、さつき、山躑躅、楓、銀杏、紫陽花等)
{別庭の奥でジャガイモを2回ほど収穫したが、今はブルーベリーの苗木を植えている。
1か月の滞在では残念だが思うように育っていない。}
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
②山荘玄関上(山荘に在住の場合に掲示) 北原教授篆刻作品「蘭亭山荘」海山著
幸喜洋人先生指導
蘭亭は中国浙江省紹興市の蘭渚山麓にあり、東晋の書家王羲之(おうぎし)が文人を集めて宴を開く。
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
③山荘 3者のコラボ作品 と 母の箪笥 母好みの琉球畳
北原教授篆書と寿紗代先生ガラスプレートと小椋弘氏の高野槇木製額
” 岳 を 表現している ””
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
④山荘 和室の掛け軸 所縁のある「蘭の墨絵」
蘭(科)は、単子葉植物の科のひとつで、その多くが美しく、独特の形の花を咲かす。世界に15000種、日本に230種がある。鑑賞価値が高いものが多く、栽培や品種改良が進められる。
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑤山荘 仏間の上の横額 「剣道士磨墨」
リーダー(士)の あるべき姿が書かれている。
「磨墨」は 中国の墨子によっている。 地域社会のため、人としての道・勉学を研鑽することを意味している。
⇒https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%A8%E5%AD%90
「剣道士」は 人のため世の中を改善しようとする 政治家等の"胆識”あるリーダーの 行動・覚悟を意味している。
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑦山荘 琉球をイメージする墨絵横額 「芭蕉と雀・野菊」
初めて 祖父の部屋で この墨絵の巻紙を観たときは、架空題材をとらえたものと思った。しかし 沖縄に移住し 沖縄の城をめぐる中で「芭蕉」「雀」・「野菊」は まさに沖縄の地のものだとの気づき驚いた。 沖縄・長野の赤い糸のような結びつき・・・ ・・ ・ 大切にしたい。
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑧山荘 母好みの 日本間 襖(表・裏)
母は 今年で90歳を迎える 理髪師をしていたが デザイナーになりたかったそうである。
名古屋生まれであったが 年少のころ 叔父の所に引き取られて大切に育てられたようだ。
小学校に行くときは、何時も 丸に引き両の紋(新田源氏の紋?)のある着物を着て馬に乗せられ
通ったと少しいやな顔をみせて語ったことを覚えている。
・・
そういえば、私の少年期 刺繍の襟のある仕立てられたシャツ等を母から よく着せられた。
料理も ケチャップライス など あの当時の 山村ではモダンな人であった。
{{襖は手品師 たった1センチメートルで異次元の空間を創る。}}
山荘の日本間は8畳が2つある。”襖の表・裏”で2つの違った雰囲気の日本間が出現。
襖を取り去れば 16畳の広間となる。
襖のデザイン紙は 40年ほど前に 母が選んだものである。母の美的センスが伺える。
表:
裏:
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑨山荘 祖母に伝えられた銅鏡
銅鏡には「厄除けの南天の木、梅の木、笹」などが描かれている。
「上藤原久共」との刻印がある。
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
⑩山荘 日本刀・脇差(警察署に届け済)・バックは蘭亭深山の書・屏風
{陶芸家:上江洲茂生先生作陶「片口泡盛大杯」}
{義弟たちが許可を得て狩猟した日本カモシカ角の刀掛け}
私が34歳の時 10年以上 胃癌で闘病していた父が亡くなった。 日本間の 父の遺体の胸の上には 祖父が日本刀を横に置いていた。 日本刀をみると鞘から少し出されて抜き身がキラリと光って見えた。 その時に 魔物等を避けるための先祖から続く作法であると祖父から諭された。 このことは今でもはっきりと脳裏に残っている。 また、父が亡くなって10年後、遺骨を分骨し京都の本山へ 母たちと納骨しに訪れた ・・・ ・・ ・ 人生 普段の生活からは窺い知れない決まり事が多くあるものだ。
・・父の死を通して 守り刀として日本刀を保持している意味等を知った・・・ ・・ ・
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
家には歴史・人の温もり等がある。 人の生き様、伝統の品々、周りの自然等も含め全てArts である。
大切にしなくてはいけない事 ” 伝える ”・・・ ・・ ・ !!!
{{蘭亭山荘 Art museum は → 蘭亭山荘 Art museumⅡ(能・小面のこころ) へ続く}
☛ https://kitahara.ti-da.net/e5312078.html
Posted by 蘭亭山荘主人(北原秋一) at 06:59│Comments(0)
│◎Cabin「蘭亭山荘」館