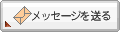2013年10月19日
北原秋一の ARTの世界 (作品)
北原秋一の ART 創作の世界に ようこそ!!!
彫刻も作陶も絵画も篆刻も書道も ・・・ ・・ 音楽も文学も ・・・ ・・ ・
・・・ ・・ 地球のように 円(縁)のように 全てが 繋がっています ***
(現在 手元に残っている 北原秋一の ART 作品です。どうぞご高覧ください。)
音楽はカテゴリー「創作した楽曲・スケッチ」を。文学はカテゴリー「琉球城紀行・城」をご覧ください。
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***

↑
(① 北原秋一 小学校6年生時の創作: 猫をモデルにした ”木彫 の 虎” )

↑
{② 北原秋一 千葉県風土記の丘で作陶 金銀彩花入「縄文印土器(注1)」 :高さ25cm }
「(注1):縄文土器(じょうもんどき)は、北海道から沖縄諸島を含む現在でいう日本列島各地で縄文時代に作られた土器である。縄文時代の年代は流動的ながら、約1万6000年前から約2300年前とされる。土器の年代測定技術はまだ完全には確立されていないため不確定な要素は残るが、中国湖南省で発見された1万8000年前の土器などとともに、21世紀初頭の時点において、土器として世界最古の部類に属している。(ウイキペデイアより抜粋。)」

↑
(③ 北原秋一作陶の織部釉・変玄皿 と 30年前 中国・広州で買い求めた”玉のシーサー”)
織部釉 は 大好きな 釉薬

↑
{④ 北原秋一作陶の アルファベット大皿 径23cm :千葉県在住時 }
大胆なイニシャル・デザイン

{⑤ 北原秋一 作陶 「”吉”茶碗」 径12cm :千葉県在住時 }
日常のご飯茶わんとして利用

↑
{⑥ 北原秋一 篆刻作品「蘭亭山荘」海山著:篆書・篆刻は幸喜洋人先生指導}
(蘭亭は中国浙江省紹興市の蘭渚山麓にあり、東晋の書家王羲之(おうぎし)が文人を集めて宴を開く)
「参考:篆書体(てんしょたい)は漢字の書体の一種。「篆書」「篆文」ともいう。広義には秦代より前に使用されていた書体全てを指すが、一般的には周末の金文を起源として、戦国時代に発達して整理され、公式書体とされた小篆とそれに関係する書体を指す。公式書体としての歴史は極めて短かったが、現在でも印章などに用いられることが多く、「古代文字」に分類される書体の中では最も息が長い。ウイキペデイアより引用。」

↑
{⑦ 北原秋一素描:仏陀像}

↑
{⑧ 北原秋一素描:南アルプス・甲斐駒ケ岳 残照}

↑
{⑨ 北原秋一素描:千葉県東金市 八鶴湖畔}

↑
{⑩ 北原秋一山岳写真:百名山・南アルプス・赤石岳:T家所蔵}

↑
{⑪ 北原秋一山岳写真:日本百名山・平ケ岳山頂付近}

↑
{⑫ 北原秋一油彩:習作:T家所蔵}

↑
{⑬ 北原秋一篆刻作品 ”北原秋一蔵書印”)

↑
{⑭ 北原秋一書: 『論語』の学而篇から}
(意味すること:若い人達には次のことを望みたい。まず親に対して孝をつくし兄弟は仲良くする。すべての面で慎重に行動し嘘をつかないこと、さらに他人には愛情をもって接し立派な人物について教えをうける。その上で余裕があれば本を読むことである。)

↑
{⑮ 北原秋一作陶 ”織部複釉・抹茶楽遊茶碗(注2) 銘 「瀧」 径Ⅰ2cm}
「(注2):楽焼(らくやき)は、一般的に電動轆轤や足で蹴って回す蹴轆轤(けろくろ)を使用せず手とへらだけで成形する「手捏ね」(てづくね)と呼ばれる方法で成形した後、750℃ - 1,100℃で焼成した軟質施釉陶器である。また、楽茶碗などとも呼ばれる。狭義には樂家の歴代当主が作製した作品や樂家の手法を得た金沢の大樋焼や京都の玉水焼などが含まれる。広義には同様の手法を用いて作製した陶磁器全体を指す。千利休らの嗜好を反映した、手捏ねによるわずかな歪みと厚みのある形状が特徴である。茶碗や花入、水指、香炉など茶道具として使用される。(ウイキペデイアより)」

↑
{⑯ 寿紗代先生製作「ガラスボード」、小椋弘氏木製飾り枠、北原秋一「篆書:蘭亭山荘」}
長野 蘭亭山荘所蔵 (木板は デザインは山容を 材料は 木曽の5木の一つ高野槇)
彫刻も作陶も絵画も篆刻も書道も ・・・ ・・ 音楽も文学も ・・・ ・・ ・
・・・ ・・ 地球のように 円(縁)のように 全てが 繋がっています ***
(現在 手元に残っている 北原秋一の ART 作品です。どうぞご高覧ください。)
音楽はカテゴリー「創作した楽曲・スケッチ」を。文学はカテゴリー「琉球城紀行・城」をご覧ください。
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***
↑
(① 北原秋一 小学校6年生時の創作: 猫をモデルにした ”木彫 の 虎” )
↑
{② 北原秋一 千葉県風土記の丘で作陶 金銀彩花入「縄文印土器(注1)」 :高さ25cm }
「(注1):縄文土器(じょうもんどき)は、北海道から沖縄諸島を含む現在でいう日本列島各地で縄文時代に作られた土器である。縄文時代の年代は流動的ながら、約1万6000年前から約2300年前とされる。土器の年代測定技術はまだ完全には確立されていないため不確定な要素は残るが、中国湖南省で発見された1万8000年前の土器などとともに、21世紀初頭の時点において、土器として世界最古の部類に属している。(ウイキペデイアより抜粋。)」

↑
(③ 北原秋一作陶の織部釉・変玄皿 と 30年前 中国・広州で買い求めた”玉のシーサー”)
織部釉 は 大好きな 釉薬

↑
{④ 北原秋一作陶の アルファベット大皿 径23cm :千葉県在住時 }
大胆なイニシャル・デザイン

{⑤ 北原秋一 作陶 「”吉”茶碗」 径12cm :千葉県在住時 }
日常のご飯茶わんとして利用
↑
{⑥ 北原秋一 篆刻作品「蘭亭山荘」海山著:篆書・篆刻は幸喜洋人先生指導}
(蘭亭は中国浙江省紹興市の蘭渚山麓にあり、東晋の書家王羲之(おうぎし)が文人を集めて宴を開く)
「参考:篆書体(てんしょたい)は漢字の書体の一種。「篆書」「篆文」ともいう。広義には秦代より前に使用されていた書体全てを指すが、一般的には周末の金文を起源として、戦国時代に発達して整理され、公式書体とされた小篆とそれに関係する書体を指す。公式書体としての歴史は極めて短かったが、現在でも印章などに用いられることが多く、「古代文字」に分類される書体の中では最も息が長い。ウイキペデイアより引用。」

↑
{⑦ 北原秋一素描:仏陀像}

↑
{⑧ 北原秋一素描:南アルプス・甲斐駒ケ岳 残照}

↑
{⑨ 北原秋一素描:千葉県東金市 八鶴湖畔}
↑
{⑩ 北原秋一山岳写真:百名山・南アルプス・赤石岳:T家所蔵}
↑
{⑪ 北原秋一山岳写真:日本百名山・平ケ岳山頂付近}
↑
{⑫ 北原秋一油彩:習作:T家所蔵}
↑
{⑬ 北原秋一篆刻作品 ”北原秋一蔵書印”)
↑
{⑭ 北原秋一書: 『論語』の学而篇から}
(意味すること:若い人達には次のことを望みたい。まず親に対して孝をつくし兄弟は仲良くする。すべての面で慎重に行動し嘘をつかないこと、さらに他人には愛情をもって接し立派な人物について教えをうける。その上で余裕があれば本を読むことである。)
↑
{⑮ 北原秋一作陶 ”織部複釉・抹茶楽遊茶碗(注2) 銘 「瀧」 径Ⅰ2cm}
「(注2):楽焼(らくやき)は、一般的に電動轆轤や足で蹴って回す蹴轆轤(けろくろ)を使用せず手とへらだけで成形する「手捏ね」(てづくね)と呼ばれる方法で成形した後、750℃ - 1,100℃で焼成した軟質施釉陶器である。また、楽茶碗などとも呼ばれる。狭義には樂家の歴代当主が作製した作品や樂家の手法を得た金沢の大樋焼や京都の玉水焼などが含まれる。広義には同様の手法を用いて作製した陶磁器全体を指す。千利休らの嗜好を反映した、手捏ねによるわずかな歪みと厚みのある形状が特徴である。茶碗や花入、水指、香炉など茶道具として使用される。(ウイキペデイアより)」
↑
{⑯ 寿紗代先生製作「ガラスボード」、小椋弘氏木製飾り枠、北原秋一「篆書:蘭亭山荘」}
長野 蘭亭山荘所蔵 (木板は デザインは山容を 材料は 木曽の5木の一つ高野槇)
この記事へのコメント
⑪北原教授書:『論語』の学而篇部分
親を大切にし
正直に人と接し
他人にやさしく
日頃、いろいろな事象に流され、視野が狭くなりがちですが、
上記の内容を肝に銘じて、日々精進したいと思います。
ありがとうございます!
親を大切にし
正直に人と接し
他人にやさしく
日頃、いろいろな事象に流され、視野が狭くなりがちですが、
上記の内容を肝に銘じて、日々精進したいと思います。
ありがとうございます!
Posted by Naha,T at 2013年10月19日 18:24
多趣味で羨ましいです。
無趣味の者としては、唸るだけです。
無趣味の者としては、唸るだけです。
Posted by 城間彩乃 at 2013年10月22日 11:55